
9月1日「防災の日」に考えたい!家庭での防災対策

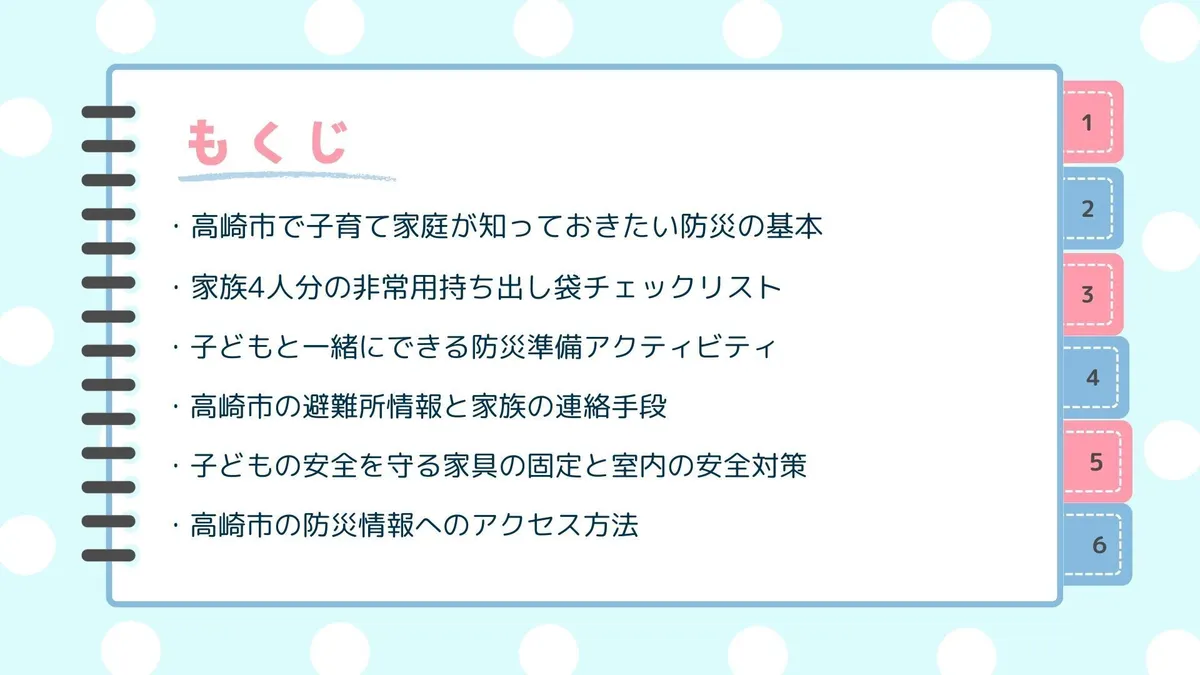
9月1日は「防災の日」
防災に対する意識を高め、「いざという時」の為に防災に備える日となります。特に小さなお子さんがいるご家庭では、防災対策が後回しになりがちです。この記事では、忙しいママさんでも、子どもと一緒に楽しみながらできる防災準備や、家族4人分の非常用持ち出し袋の作り方をご紹介します。
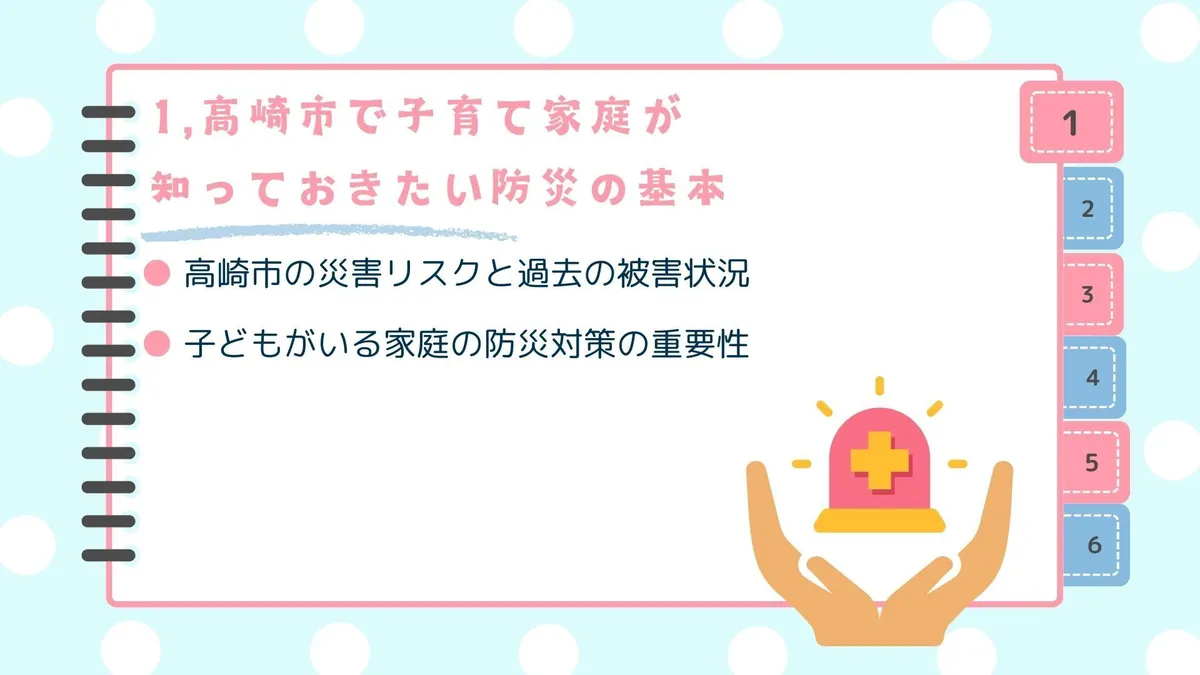

災害はいつ起きるか分からないからこそ、地域特有のリスクを知り、家族全員が“自分ごと”として備えることが大切です。
高崎市の災害リスクと過去の被害状況
高崎市では、地震や台風にともなう豪雨被害が主なリスクとして挙げられます。たとえば、2019年の台風19号では市内各地で住宅の浸水や道路冠水が相次ぎ、榛名地域では土砂災害も発生しました。
特に、烏川や井野川の周辺など低地に位置する地域は、今も浸水リスクが高いとされています。
まずは、お住まいの地域がどんなリスクを抱えているかを知ることが、防災の第一歩になります。
子どもがいる家庭の防災対策の重要性
災害時、小さなお子さんは状況を把握したり、自分で避難したりすることが難しいもの。だからこそ、大人が慌てずに行動するための準備がとても重要です。
赤ちゃんがいる家庭では、粉ミルクやおむつ、離乳食など「子ども専用の備蓄リスト」をつくっておくと安心です。また、防災訓練を“家族のイベント”として楽しみながら取り入れれば、子どもたちも自然と災害時の行動を身につけることができます。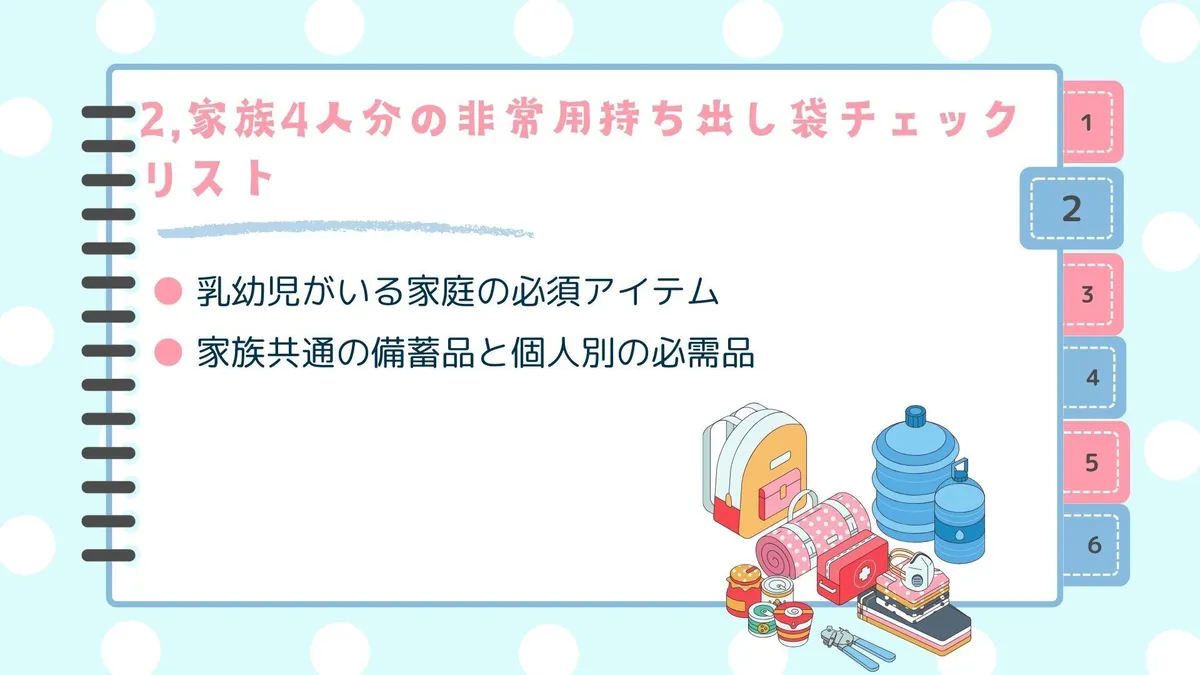
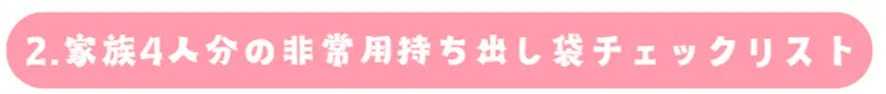
家族全員が安心して避難生活を送るための持ち出し袋の内容を確認していきましょう。
乳幼児がいる家庭の必須アイテム
0〜5歳のお子さん用に準備したいものには、粉ミルク(キューブタイプが便利)、哺乳瓶、おむつ(3日分)、おしりふき、着替え、抱っこひもがあります。幼児用には、お気に入りのぬいぐるみや絵本など、不安を和らげるアイテムも大切です。子どもの成長に合わせて定期的に中身を見直しましょう。
家族共通の備蓄品と個人別の必需品

家族共通で必要なものは、水(1人1日3リットル)、非常食、モバイルバッテリー、懐中電灯、ラジオ、救急セット、ウェットティッシュです。個人別には、常備薬、眼鏡、生理用品など、その人特有の必需品を用意しましょう。家族全員分の健康保険証のコピーや現金も忘れずに。
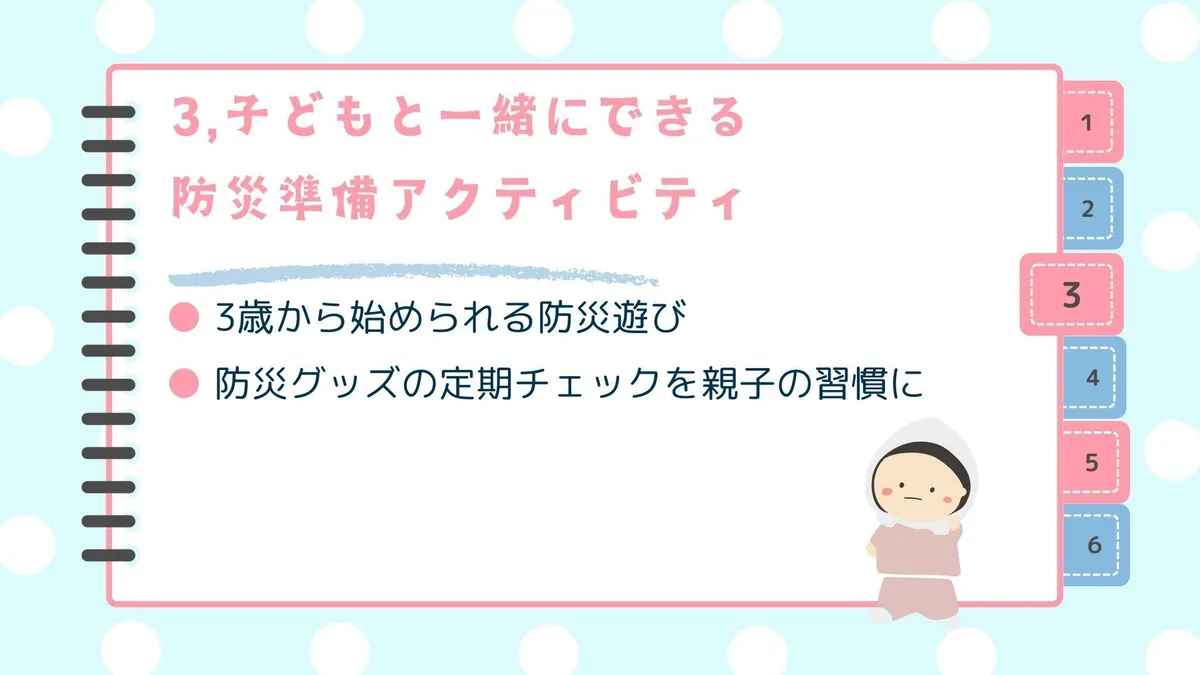
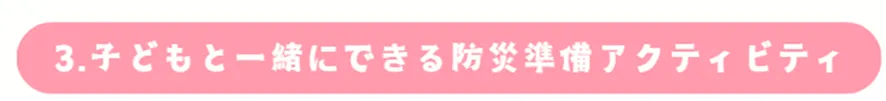
防災準備は親子で楽しく取り組めるファミリーイベントにしましょう。
3歳から始められる防災遊び

3歳を過ぎたら、「地震ごっこ」で「じしん!」の掛け声と共に机の下にもぐる練習ができます。「お・か・し・も」(おさない、かけない、しゃべらない、もどらない)のルールも歌にして教えると覚えやすいですよ。「暗闇探検」として夜に電気を消して懐中電灯だけで過ごす時間を作れば、停電時の行動を体験できます。
防災グッズの定期チェックを親子の習慣に
カレンダーに「防災グッズチェックの日」を子どもと一緒に書き込んでおくと、子どもも楽しみにしてくれます。点検の際は、懐中電灯のスイッチ操作や非常食の袋の開け方など、実際に触れさせることが大切です。古くなった非常食を使った料理日を設けると、無駄にせず楽しく交換できますよ。
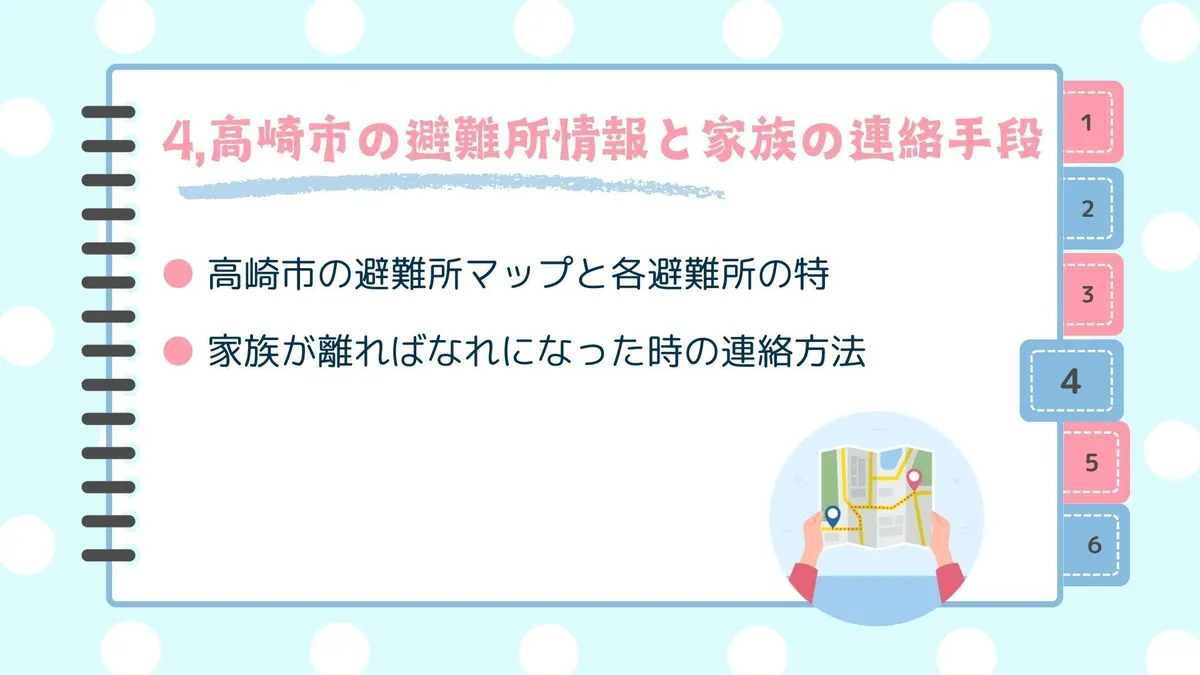
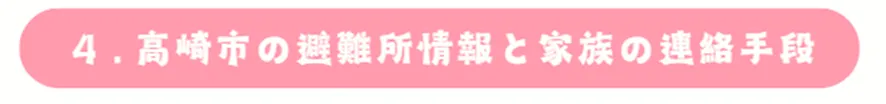

事前に避難所の場所を確認し、家族間の連絡方法を決めておきましょう。
高崎市の避難所マップと各避難所の特徴
高崎市には約120カ所の避難所があり、高崎市ホームページの「高崎市指定避難所」ページで確認できます。自宅近くの避難所を実際に家族で訪れて、入口やトイレの位置、バリアフリー対応の有無などを確認しておくと安心です。子どもと一緒に「避難所探検」として週末のお散歩コースにしてみてはいかがでしょうか。
参考:高崎市「高崎市指定避難所」(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3346.html)
家族が離ればなれになった時の連絡方法
災害時は「災害用伝言ダイヤル171」と「災害用伝言板」が役立ちます。災害用伝言ダイヤル171は、固定電話や携帯電話から「171」をダイヤルし、ガイダンスに従って伝言の録音・再生を行うサービスです。
また、携帯電話各社が提供する「災害用伝言板」は、被災地の方が文字で伝言を登録し、携帯電話番号を利用して全国から伝言を確認できるサービスです。これらの使い方を家族全員で練習しておきましょう。
子どもには自分の名前、親の名前、住所や電話番号を覚えさせておくと、もしも迷子になった時に役立ちます。防災カードを作って、子どもの靴やバッグに入れておくのもいい方法です。
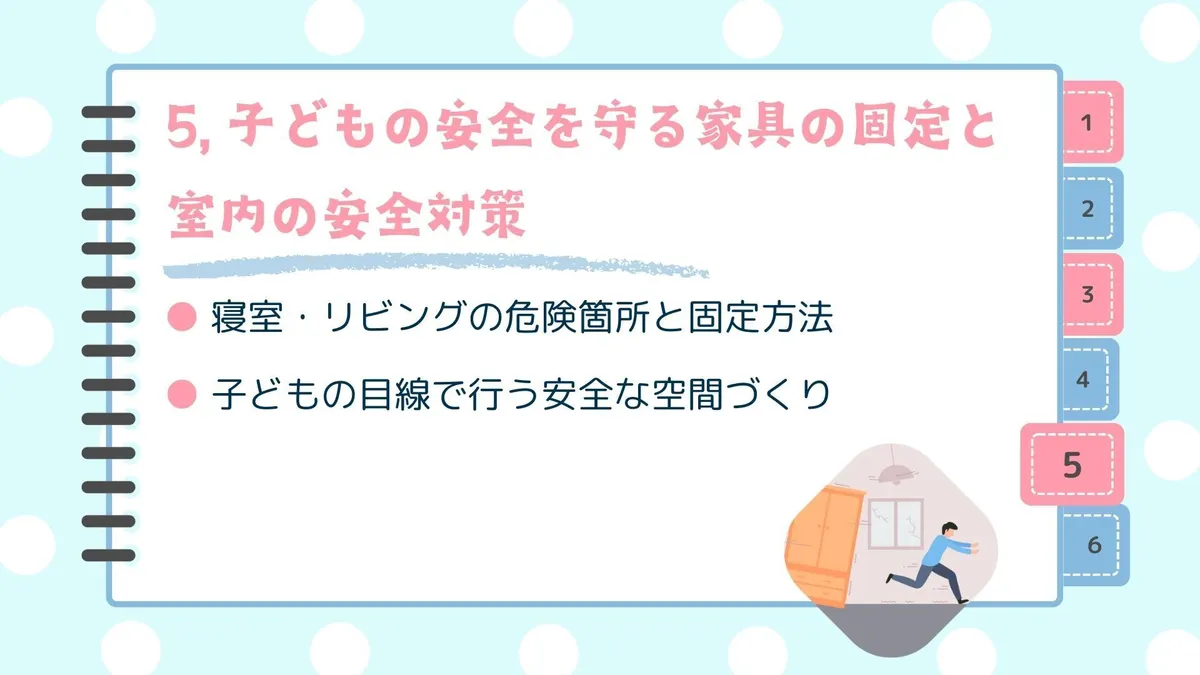

小さな子どもがいる家庭では、子どもの目線に立った安全対策を行いましょう。
寝室・リビングの危険箇所と固定方法
背の高い本棚、タンス、食器棚、テレビは優先的に固定しましょう。L字金具や突っ張り棒、賃貸住宅でも使える粘着式の固定具も便利です。高崎市では、18歳未満の子どもがいる世帯を対象に、家具転倒防止器具の取り付け支援事業を行っています。市役所の防災安全課に問い合わせてみてください。
子どもの目線で行う安全な空間づくり
子どもと同じ高さでハイハイやしゃがんで室内を見渡してみましょう。子どもが触れる高さにある危険なものや、倒れやすい家具に気づくはずです。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼り、避難経路となる廊下や階段には物を置かず、常に通れるようにしておきましょう。
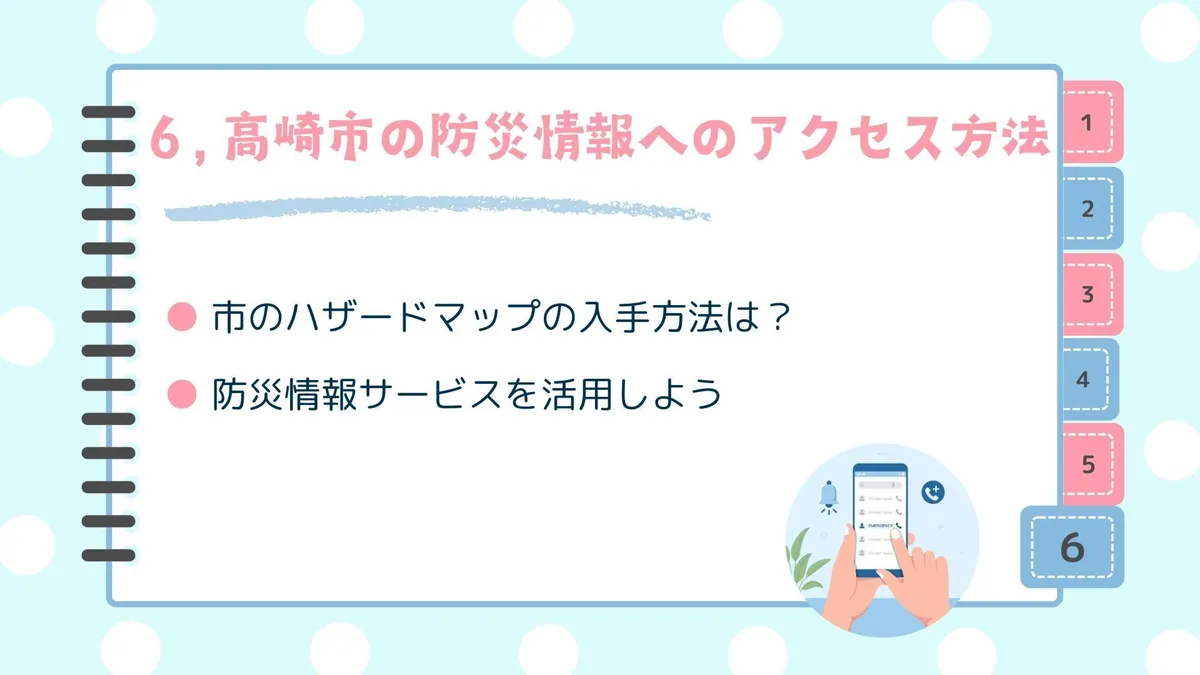
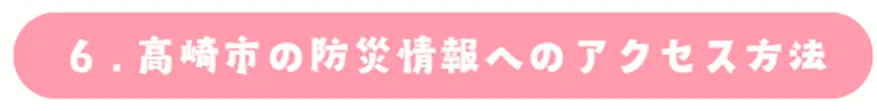
いざというときに役立つ防災情報を事前に入手しておきましょう。
市のハザードマップの入手方法は?
高崎市のハザードマップは、市のホームページからPDF版をダウンロードできるほか、全世帯への配布や転入者への配布も行われています。自宅の位置を確認し、周辺の危険度や避難所の位置をチェックしましょう。台所やリビングの見えやすい場所に貼っておくと、日頃から家族の防災意識を高められます。
参考:高崎市「高崎市ハザードマップ」(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3242.html)
防災情報サービスを活用しよう
高崎市では「たかさき安心ほっとメール」というサービスを提供しており、登録すると防災情報や気象情報などをメールで受け取ることができます。また「高崎市LINE公式アカウント」でも生活に役立つ情報や防災情報を受け取ることができます。スマートフォンの「緊急速報メール」の設定も必ずオンにしておきましょう。
参考:高崎市「安心ほっとメール」(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/2002.html)
参考:高崎市「高崎市LINE公式アカウント」(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3127.html)
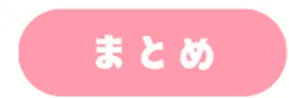
小さなお子さんがいる高崎市の家庭における防災対策のポイントをご紹介しました。防災準備は一度にすべてを完璧にする必要はありません。非常用持ち出し袋の準備、家具の固定、避難所の確認など、一つひとつ対策を積み重ねることで、いざというときの安心につながります。今日から少しずつ、子どもと一緒に楽しみながら進めていきましょう。




